・簿記3級の取得を目指している人
・簿記の勉強をするか迷っている人
・資産形成に取り組んでいる人
こんにちは。優です。
簿記3級は多くの社会人にとって何らかの役に立ち、履歴書にも記載できることから取得を目指す人の多い資格です。
私も
「投資のために企業の財務諸表を見てしっかりと理解できるようになりたい」
「簿記の知識を身につければ仕事に役立ちそうだ」
という思いから勉強を始め、2025年2月23日の簿記検定試験で3級に合格することができました。
この記事では、普段から資産形成に取り組んでいる私が、実際に簿記を勉強して感じた『簿記の知識が資産形成に与える影響』について紹介します。
なお、以下の2点について、あらかじめご了承いただけますと幸いです。
・私が勉強した簿記3級の範囲内でのお話であること
・ややこじつけと感じられる部分があるかもしれないこと
簿記の勉強が資産形成に与える影響
①家計管理に簿記の考え方を取り入れられるようになる
資産形成に取り組んでいるかどうかに関わらず、家計簿などで家計管理をしている人は多いでしょう。
通常の家計簿は、
・何にお金を使ったのか
・何によってお金が増えたのか
・ある期間にいくらお金を使ったのか(あるいは増えたのか)
・現在いくらお金が残っているのか
といった、お金の増減や残高のみを記録するものです。
一方、簿記を学ぶことで、お金を支出したことによって増えたモノ(有形固定資産)についても意識できるようになります。
たとえば、車を購入した場合は以下のように考え方が変わります。
簿記を学ぶ前
車を買ったからお金が100万円減った(単に「100万円を支払った」という考え方)
簿記を学んだ後
お金は100万円減ったが、車という100万円分の有形固定資産を手に入れた(「100万円を車という価値ある資産と交換した」という考え方)
これは車に限らず、家電や家具、洋服などについても同様に考えることができます。
家計管理に簿記の考え方を取り入れることで、支出に対する認識を「お金が減った」から「お金は減ったけど、別の価値あるモノ(資産)を手に入れた」へと変えることができます。
(食べ物や消耗品を買ったときには取り入れにくい考え方ではありますが…)
さらに現在では、メルカリ、ラクマ、Yahoo!フリマといったフリマアプリや、リサイクルショップなどの出張買取サービスが充実しているため、いざというときには保有している資産を現金化することも可能です。
あなたの身の回りにも、お金以外に価値ある資産が数多く存在するはずであり、簿記の学習はそれらの存在に気づくきっかけになるでしょう。
まとめると、簿記を学ぶことで家計管理において次のような変化や気づきが生まれます。
・モノを購入する際の考え方が変わる
・お金以外にも、価値ある資産が身近に存在することに気づく
ただし、「お金は減るけれど、その分価値のある資産が増えるのだから、どんどんお金を使っても大丈夫だ」といった誤った思考に陥らないよう、注意が必要です。
有形固定資産
長期にわたって使用する形のある資産
例)土地、建物、車両、パソコンや棚などの備品
②有形固定資産(車や持ち家)の減価償却を意識するようになる
資産形成や節約に取り組んでいると、
「持ち家か賃貸か」
「車を所有すべきかどうか」
といった話題に触れる機会が多いと思います。
どちらが良いかは個人の状況や価値観によって異なるため、ここでは詳しくは触れませんが、簿記を学ぶことで減価償却を意識するようになり、家や車の購入・所有に対してより慎重になる傾向があると感じます。
あくまで簿記における考え方ですが、持ち家や車などの有形固定資産は、時間の経過とともに価値が減少していきます。
たとえば、新車の普通自動車を300万円で購入した場合、減価償却によって毎年価値が下がり、6年後には帳簿上は無価値になるという扱いになります。
「購入した瞬間から価値は減少し、最終的には無価値になる」という考え方が頭の片隅にあるだけでも、それまで高い価値があると思っていたモノの見え方が少し変わってくるかもしれません。
また、家や車の購入が「投資」なのか「消費(あるいは浪費)」なのかについても考えられるようになります。
たとえば、最終的に売却する前提で考える場合、売却によって利益が見込める(減価償却後の帳簿価格<売却額)のであれば、購入は「投資」と見なせます。
一方、売却によって損失が出る(減価償却後の帳簿価格>売却額)のであれば、「消費」あるいは「浪費」と捉えることになります。
・200万円で売れた ⇒ 50万円の利益が出たため、新車購入は投資と見なせる
・100万円で売れた ⇒ 50万円の損失が出たため、新車購入は消費または浪費と見なされる
実際にここまでの損益計算をして買い物をするかどうかはさておき、簿記を学ぶことで、家や車といった有形固定資産の価値を、”保有期間中の価値減少も含めた長期的な視点で考えるようになる”でしょう。
とはいえ、車や家には数値化できる価値以外にも、
・車を所有することによる利便性の向上
・持ち家という、自分たちだけの居場所があるという安心感
といった要素もあるため、ここで紹介したような簿記的な考え方に過度にとらわれすぎないよう注意が必要かなと思います。
減価償却
固定資産の価値減少分を帳簿上の固定資産の価値から減額し、同額を費用として計上する会計処理
耐用年数
その固定資産を取得した時から何年使えるかという「固定資産の利用可能年数」のこと
新車の普通自動車の法定耐用年数は6年(取得後6年で無価値になる)
③借金や利息の支払いをより避けるようになる
本格的に資産形成に取り組んでいる人であれば、借金によって利息を支払わなければならない状況を極力避けようとしていると思いますが、簿記を学ぶことで利息の支払いに対してより敏感になると感じました。
たとえば、借金返済で毎月一定額を支払っている場合、銀行口座やクレジットカードの利用明細から支払総額は確認できても、その中の利息分がいくらかは、内訳を詳細に見ないとわからないことが多いと思います。
そのため、支払った金額のうち何円が利息にあたるのかを正確に把握するのは難しいでしょう。
実際、借金を返済している人のなかには、自分が利息を支払っているという認識がない人もいるかもしれません。
簿記では、借りたお金の元本は「借入金(負債)」、支払った利息は「支払利息(費用)」といった別々の勘定科目で記録します。
そのため、簿記を学ぶことで「借金をすると負債だけでなく費用(生活費)も増える」という考え方を持つようになり、自分がどれだけ利息を支払っているのかを意識するきっかけになります。
それによって、不要な借金を避けるための抑止力として働くことも期待できるでしょう。
勘定科目
簿記で使われる、取引を処理するための用語
④手数料の支払いにより敏感になる
基本的には、利息に対する考え方と同様です。
支払った手数料は、簿記では「支払手数料(費用)」として扱われるため、「手数料を支払う=生活費が増える」という認識が強まると思います。
手数料の代表例としては、「ATMの入出金時の手数料」や「分割払いの手数料」が挙げられます。これらは明細に記載されることが多いため、簿記を学んでいなくても普段から意識している人も多いかもしれません。
ただし、投資信託の信託報酬のように、支払っていることを自覚しにくい手数料もあります。
簿記を学ぶことで、そうした見えにくい手数料を再認識するきっかけになるかもしれません。
(資産形成の勉強にしっかり取り組んでいる人であれば、そもそも信託報酬の低い投資信託を選んでいる可能性が高いとは思いますが……)
⑤個別株投資における銘柄選定の難易度が下がる
資産形成のために株式投資を行う人は多くいます。
株式投資は、
・インデックス投資(様々な企業の株の詰め合わせパックを購入する投資方法)
・個別株投資(どの企業の株を購入するかを自分で選ぶ投資方法)
の2つに大別されますが、簿記の知識は特に個別株投資で役立ちます。
個別株投資では、気になった企業の財務状況や持続性、成長性などを自分で分析し、株を購入するかどうかを判断する必要があるため、一般的に難易度が高めです。
しかし、簿記を学ぶことで、企業の貸借対照表や損益計算書の内容をある程度理解できるようになり、
「どのくらい利益を出しているのか」「どれほどの借入があるのか」といった企業の財務状況を把握しやすくなります。
その結果、個別株投資における銘柄選定の難易度が下がります。
貸借対照表
ある時点における企業の財政状態を表す書類
損益計算書
一定期間にいくら使って、どれだけ儲けたかといった、企業の経営成績を表す書類
まとめ
『簿記の勉強が資産形成に与える影響』について紹介してきました。
最後にポイントを簡単に整理しておきます。
① 家計管理に簿記の考え方を取り入れられるようになる
・お金を支払う(モノを購入する)際の考え方が変わる
・お金以外にも、自分の身の回りに価値ある資産が存在することに気づくきっかけになる
② 有形固定資産の減価償却を意識するようになる
・有形固定資産の価値を、保有期間中の価値減少も含めて長期的に捉えるようになる
・有形固定資産の購入が「投資」か「消費(浪費)」かを判断できるようになる
③ 借金や利息の支払いをより避けるようになる
・「借金をすると負債だけでなく費用(生活費)も増える」と考えるようになる
④ 手数料の支払いにより敏感になる
・「手数料を支払う=生活費が増える」という認識が強まる
・普段支払っている手数料を再認識するきっかけになる
⑤ 個別株投資における銘柄選定の難易度が下がる
・貸借対照表や損益計算書から、企業の財務状況を把握しやすくなる
簿記の知識は、仕事に役立つだけでなく、資産形成にも大いに活かせます。
簿記を学んで損をすることはほとんどありません。
少しでも興味がある方は、まずは簿記3級の内容から学んでみてはいかがでしょうか。

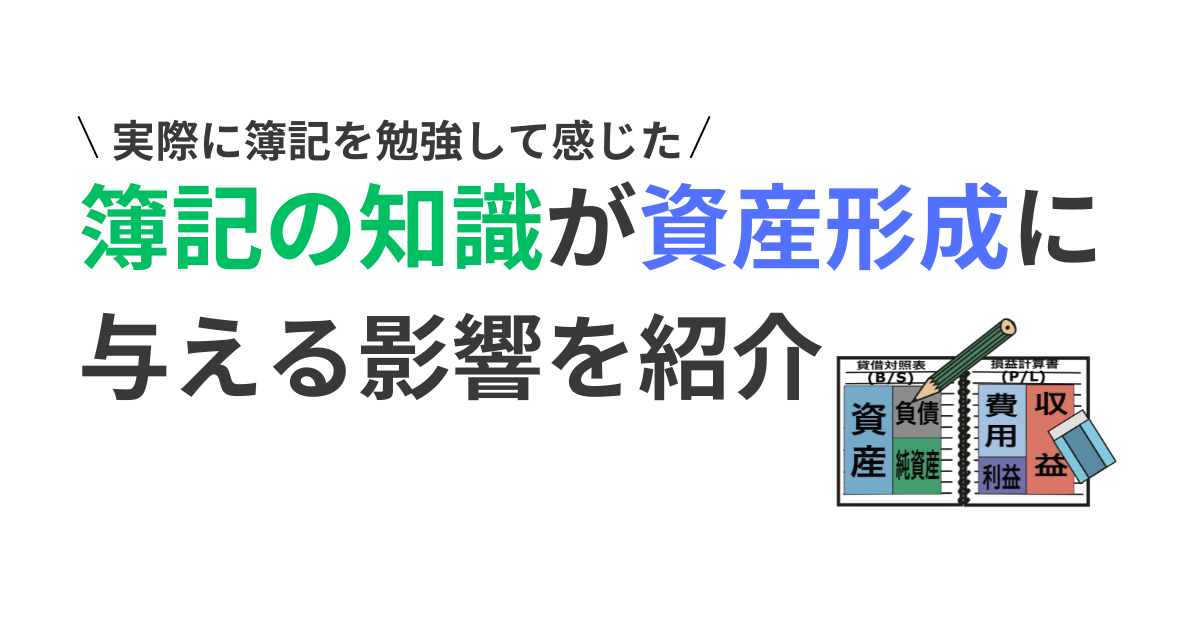
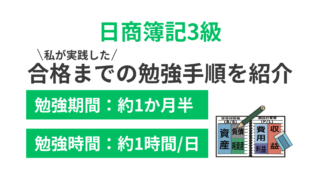

コメント